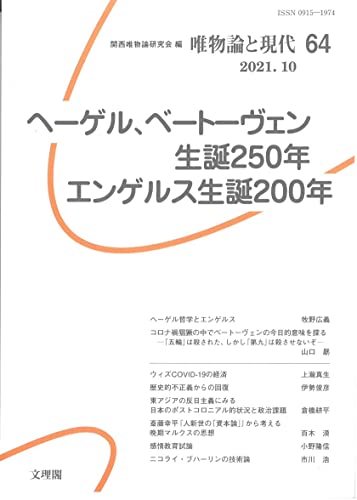オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」が話題になっているようです。私も署名しているので、改めて読み返したのですが、問題点がどこにあるのかわからないので困惑しています。オープンレターは以下で公開されています。
オープンレターは、日本語圏の言説空間において、性差別を指摘する行為をからかったり揶揄する「遊び」の文化があることを指摘しています。そして、そこから距離を取ることを宣言しています。私はこのオープンレターのきっかけとなった、ある歴史学者による差別行為、さらにそれを多くの研究者が加担したり、見て見ぬふりをしたりしていたことに強い衝撃を受けました。以前から書いていますが、私はほぼ衝動的にそれまで使っていたTwitterのアカウントを消しました。自分もその文化の一翼にいたのだろうし、自分自身もそれに加担しているのかもしれないというのは恐怖でしかなかったからです。ただし、この行為が合理的であったのかどうかは、わかりません。
私がそれほど衝動的になってしまったのは、その件が、今まで私自身が遊びの対象にされてきた数々の場面を一気に思い出させるものだったからです。私は、大学に入学して以降、性差別に抵抗するたびに、男性の先輩、同級生、ときには教員から嘲笑されました。2000年代前半はフェミニズムの勢いはとても弱くなっており、私に賛同したり味方になったりする人は、ほとんどいませんでした。かれらは、私が動揺しながら性差別を指摘する喋り方を、真似て笑いました。肩をすくめ、目配せしあい、ニヤニヤと笑う、というのもよくありました。いじめの標的になったことがある人は理解しやすいと思うのですが、私は今でも男性が集まって笑っているのを聞くと、「私がネタにされているのだろうか」と不安になることがあります。そして、その場から黙って去ることがあります。当時、私が真剣にかれらに抗議すれば、かれらはこう言いました。
「ネタだよ、ネタ」
そういう言い回しが、2000年代前半は流行っていました。2ちゃんねるを中心とするネット文化の影響もあったのでしょう。かれらにとって、私の取り乱した姿を見て笑うのは、本気ではなく「遊び」だったのです。多くのいじめがそうであるように。
その後、大学院進学後に学会で起きたこと。私はそのひとつひとつは、まだ書く力は私にはありません。いくつかの痛みを覚える記憶が私にはあります。
私は、オープンレターのきっかけになった出来事でも、関わった人たちは同じように思っていたのではないかと、予想しています。ひとりひとりは、とても良い人かもしれない。一対一で話せば、もしかすると「遊び」に関わるのをやめてくれるのかもしれない。その場の雰囲気に流されて、言ってしまったのかもしれない。私だって似たようなことをしているかもしれない。たとえば、口が滑って言いすぎたり、調子に乗って大袈裟に言ってしまったりするかもしれない。だから、かれらだって……と思うと同時、脳裏にはこう浮かびます。
「だから、なんなの?」
文化的背景がわかったところで、やられた側の痛みが和らぐわけもありません。そして、やっかいなのは、(いじめがそうであるように)ひとつひとつの言動はたいしたことがないのです。その積み重ねられたいくつもの「ちょっとした面白い言い回し」と笑いが堆積していて、標的にされた人間を押しつぶそうとしたとき、誰に責任があるのでしょうか。もちろん、実際に行為の中心になった人物でしょう。でも、その人がいなくても、次の別の人が同じ行為を始めるかもしれない。それを防ぐためには、文化を理解するだけではなく、変えなくてはなりません。
だからこそ、このオープンレターは私にとって重要だったし、署名しました。署名の責任がどうこう、裁判がどうこういうと言っている人がいるようです。もし、署名者の意図の表明が必要であれば、私はもちろん協力します。それと同時に、ほかの人たちに署名の意図を表明させるよう、圧力をかけるのはやめてほしいと思っています。自分から明かす必要もないと私は思います。私は責任感が強いのでも、勇気があるのでもありません。ただ、こういうことをしても、日本語圏のアカデミズムで何度も笑いのにされてきたので、それが一回増えるだけだという諦めがあります。そして、私より若い人、立場の弱い人には、性別を問わず、そういう諦めを受け入れてほしくはありません。どうか、身を守ってください。私も、有形無形、直接間接問わず、上の世代が守ってきてくれたから、今ここにいると思っています。これは、私の署名の釈明ではなく、脈々と続く反差別の運動への連帯の表明です。
追記
私がこういうことを書くと、以下のようなツイートに私のブログのリンクが貼られていました。火中の栗を拾うとこういうことがたくさん起きます。以下のツイートに対して、一つだけ言っておくのですが、これはポエムではなくアジ文です。私は、詩を書くほど言葉を研ぎ澄ますタイプではありません。
小松原もポエム書いてないで、ちゃんと呉座先生の地位と給料を奪うのか、雇用側が切る理由になったことを筋道つけて書けよ。学者だろ?
— 吉澤 (@yoshizawa81) 2021年12月2日
オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」について - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版) https://t.co/5SbvL628Sv
追記2
以下のようなブックメークメントがついています。
id:Akech_ergo オープンレターのうち一般論として述べられている部分については異論ないけれど、呼びかけ人に呉座氏に攻撃されていた人がおり、冒頭で呉座氏だけを名指ししている点で、氏への反撃を目的とした文章なのだなと思う。
問題の当事者が、同じようなことが起きないように文化を変えていくことを訴えることはよくあります。たとえば、性暴力被害者が、性暴力のない社会を作るように訴えたり、飲酒運転による殺人の被害者が、飲酒運転を許さない社会を作るように訴えたり、いじめの被害者が、いじめのない学校文化を作るように訴えたりします。それらを、加害者への反撃とみなす人は多くないでしょう。同様に、この件の被害者が、自分に起きた出来事を寛恕するような文化に対して、それを変えていくように訴えることは、当該事件の加害者への反撃とはみなさないのが、妥当な判断だと私は思います。なお、オープンレターの冒頭での、きっかけとなった事件への言及は、すでに公開されている情報であるため、問題はないでしょう。
追記3
ブックマークコメントがずいぶんと増えているようです。フェミニズム内部での批判については、私は何度か記事を書いていますので、興味がある人はブログ内検索で「フェミニズム」をキーワードに探して見てください。セックスワーカー差別、トランス差別についても書いています。「キモくて金のないおっさん」について書いたことはありませんが、「非モテ」で検索してもらえば、私のスタンスはわかると思います。
裁判については、オープンレターとの関連は全く不明です。11月25日に第一回公開弁論が開かれ、両者が全面的に争う姿勢のようですので、今後、新しい情報は出てくると思います。おそらく、京都新聞が地元紙なので丁寧に報道すると思います。興味がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。京都新聞は月額980円で全ての記事が読めます。
私に対して、身を案じて「弁護士に相談した方がいい」とアドバイスしてくれた人がいますが、たぶん、社会運動に参加したことがないのだろうと思います。