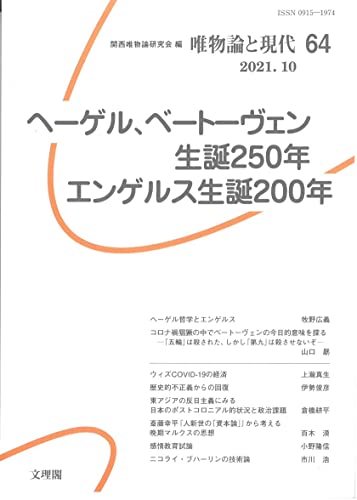伊勢俊彦「歴史的不正義からの回復 いかにして被害は語りうるものになるか」
『唯物論と現代』に掲載された論文「歴史的不正義からの回復 いかにして被害は語りうるものになるか」を著者よりご恵投いただきました。ありがとうございました。
本論文では、過去に起きた歴史的不正義について、当事者の語りをいかにして受け止めるべきなのかが検討されている。例に挙げられるのは韓国における日本軍戦時性暴力被害者(主に「慰安婦」)の語りである。著者は、移行期正義(transitional justice)と 修復的正義(restorative justice)を比較検討し、真実和解委員会が戦時性暴力をに果たす役割と、その困難について考察する。日本軍戦時性暴力の被害者の語りは、主に韓国の民間団体により記録が行われてきた。しかしながら、民間団体が継続的な活動をすることには限界があったことが指摘され、戦時性暴力の場合でも、公的機関が真実和解委員会を設置する必要があることが浮かび上がる。
他方、真実和解委員会で性暴力被害を聞き取るためには、いくつかの注意点があることを著者は述べる。まず、性暴力の被害の形態について、社会のマジョリティが抱きやすい型にはめられないように努めなくてはならない。次に、著者は小松原織香『性暴力と修復的司法』(成文堂、2017年)を参照し、「聞き手」が「語り手」とパーソナルな関係を築く対話の手法が必要だと指摘する。さらに、記録が社会的通念や公式の歴史観に沿うように整理される危険を除去しなければならないと、著者は考えている。以上の検討をもとに、日本軍戦時性暴力被害者の場合は証言者が減ってきているために、現実的な真実和解委員会の設置は困難が大きいが、同様の事例においては検討が可能であると、著者は提言している。
さらに、著者が注目するのは、戦時性暴力被害者の語りの「聞き手」である。小松原の性暴力事例における修復的正義の研究が、個人としての被害者・加害者の二者関係に焦点を絞るのに対し、歴史的不正義は組織的・集団的な人権侵害である。そのため、加害者個人の責任追求するだけではなく、集団として責任を引き受ける主体を構想することが必要となる。また、時間の経過により、直接の加害者や、命令者、国家や武装組織などが、もうこの世にないこともある。著者は、そうした場合はその責任の継承者が、被害者に対し応答せねばならないと考える。たとえば、日本軍戦時性暴力の場合は、日本国である。加えて、著者は責任主体を「国家」という抽象概念だけではなく、被害者に関わるコミュニティの人々を想定している。すなわち、関係する一人一人の人間が、被害者の聞き手になることで、語りの生成に関与するかたちで責任を負うというビジョンを提示するのである。そして、著者はそれらの語りは何度も繰り返され、継承されていくことを以下のように述べる。
(略)歴史的不正義の被害についての語りは、ある時点において完成し、最終的に不変なかたちで確立するのではない。歴史的不正義の被害は、歴史に刻まれ、時が流れ、新しい世代が生まれ、社会や政治体制のあり方が変化する、そのあらゆる段階で、繰り返し語られなければならない。語りの主体も、人権侵害行為の直接の被害者やその家族から、新しい世代へと交代していかねばならず、聴き手もまた次々に新しい世代へと変わっていく。こうした新たな話し手と聞き手の関係の中で、被害は語り直される。(68-69頁)
以上のように、著者は歴史的不正義の語りは、次世代へと継承されなければならないことを論文の末尾で示す。重要なのは、これらは記録として歴史を残すだけではなく、語り手と聞き手の関係性自体を継承していく必要を著者が述べていることである。本論文は、特に、被害の隠蔽や矮小化が行われているときには、被害者の尊厳の回復のために、語り直していくべきであると結論づけている。
この論文では、私の『性暴力と修復的司法』が論文の中で大きく取り上げられ、参照されている。この本は、私の博士論文を下敷きにした初めての単著で、至らない点も多くあり、恐縮であるが、私の提起した主体モデルを活用いただいたことに心から感謝している。
加えて、この論文には多くの刺激を受けた。第一に、「集団的な責任主体」についてである。私は博士論文を執筆後、性暴力から公害(水俣病)へと研究のフィールドを移した。その際に直面したのが、まさにこの「集団的な被害者性・加害者性」である。従来の修復的正義研究の多くは、個人と個人の対話関係に光を当ててきたが、集団的な被害・加害関係をどう扱うのかについては、まだまだ議論の途上である。私がいま、滞在しているルーヴェン・カソリック大学でも、集団的被害者性(collective victimhood)と修復的正義へ注目する研究者が増えている。
その際に、重要となるのは、まさしく著者が試みた移行期正義と修復的正義の比較である。著者は、宇佐美(2013)*1と松本(2017)*2の二論文を検討する。移行期正義と修復的正義の共通点は、被害者中心のアプローチであり、かれらの語りに焦点が当てられることになる。松本(2017)は、「慰安婦」の被害の回復のために、日本政府が事実を記録し、記憶を継承し、そのうえで金銭的賠償を行うことは、修復的正義の実現の意図が見出せると考える。他方、宇佐美(2013)は、修復的正義が被害者の癒しを強調することがあるのに対して、移行期正義における真実和解委員会は、あくまでも真実解明によって被害者の尊厳を象徴的に回復するのであり、心理的な癒しの有無は問わないと考える。両者の比較を通して、著者は次のように述べる。
松本が、明らかにされた事実にいかに対処するかを論じているのに対し、宇佐美は、事実に対処する前提として、事実がいかに明らかにされるか、その過程をも考察の範囲に含めていると言える。(59頁)
言い換えれば、移行期正義が真実の究明を優先するのに対し、修復的正義は被害者のニーズを満たすことを優先する。著者の考察に沿えば、移行期正義と修復的正義は実践レベルではよく似ているが、理念レベルでは進む方向が異なっている。
第二に「語りの継承」である。私は、まさにいま、水俣病の研究でこの問題に焦点を当てている。この問題には、おそらく「集団的被害者性」も関与している。公害が与えるコミュニティへの影響もまた、直接の被害者やその家族だけではなく、そこで暮らす人々の多くへ及ぶ。そのため、公害でも、コミュニティの歴史の一部として、残されたものが被害者の語りを継承することを、被害者自身が望むことがある。私は水俣病患者の田上義春さんの遺した、「今のままでは、患者は犬死にじゃ。払った犠牲も強いられ続けている犠牲も患者がいなくなれば、みんな忘れられてしまう。おどんたちの生きた証ばどげんかしてのこせんもんじゃろうか」という言葉を重く受け止めている。
他方、この二点について突き詰めて考えていくと、ある暴力や犯罪の被害者が、「真実」と「癒し」のどちらをもとめるのか、また「集団的」であるか「個人的」であるのかの線引きは、どこまで明確であるのかは怪しい。たとえば、性暴力被害者の多くは、修復的正義で加害者に対して「なぜ、私だったのか?(Why me?)」を問いたいと考える。つまり、被害者は癒しではなく、真実を追求することを望んでいる。加えて、家族・親族からの性暴力被害であった場合、問題が次の世代に及ぶこともある。これまで、家族の問題は「虐待の連鎖」というような言葉で、「行為」を次世代へ継承されることのネガティブな側面だけが強調されてきた。しかしながら、家族・親族関係において、親世代から子世代へ「なぜ、いまの私たちがこんなふうな関係なのか」を説明するときに、性暴力被害の記憶が語りなおされ、継承されることもあるだろう。すなわち、かれらのファミリーヒストリーのなかに、性暴力の「行為」ではなく「語り」が編み込まれる余地はあると考えられる。さらに、それに対して家族・親族の「負の歴史」を次世代へ背負わせることを批判する人もいるだろう。たとえば、親が犯罪者の場合、子は被害者の語りを聞く責任はあるだろうかーーもしかすると、「親を殺された子」が、「加害者の子ども」と話をしたいということはあるかもしれない。それは実現すべき対話だろうか、それとも避けるべきだろうか。
そう考えると、戦争や公害(環境問題)に限らず、修復的正義において、語りの世代継承の是非を問う議論は深く掘り下げている必要があるように思われる。これらの提起は、従来の修復的正義が、一世代限りの個人の関係に閉じて被害・加害関係を捉えてきたのに対し、集団的・歴史的に被害・加害関係を捉える視座を与えてくれるだろう。これは、修復的正義の新しい議論の展開をもたらし得ると、私は考えている。